ボリス・グロイス『ケアの哲学』(河村彩訳、人文書院)の刊行にちなんで、ケアと利他を考えるための本を新旧のメンバーが選びました。

キャロル・ギリガン『もうひとつの声で 心理学の理論とケアの倫理』
川本隆史他訳、風行社、2022年
現在盛んに論じられているケア論の原点となる著作。心理学者の著者は、男性(男児)と女性(女児)へのインタビューの回答を分析し、前者が「正義の倫理」に基づいて行動するのに対し、後者は人とのつながりとそこでの自分の応答を重視する傾向にあると主張する。後者の提示する価値観こそ「ケアの倫理」に他ならないが、女性に多く見られる価値観であるがゆえに不当に軽視されてきたという。学問の世界のアンコンシャス・バイアスを問う本でもある。(河村)

小川公代『ケアの倫理とエンパワメント』
講談社、2021年
自立した自己を確立することが良しとされる近代において、他者と関係し依存するというケアの価値観は、女性的であるがゆえに不当に貶められてきた。作者は古今東西の文学の中にさまざまなケアの様相を見出し、男女ともに持ち合わせている普遍的な価値観としてケアの倫理を提示する。「多孔的自己」や「ネガティヴ・ケイパビリティ」といった人間の「弱さ」を捉え直す概念が展開されることにより、文学が、弱さと強さの間で揺れ動く人間を描くのにいかに優れた芸術であることに改めて気付かされる。(河村)

神谷美恵子『ケアへのまなざし』
みすず書房、2013年
ハンセン病療養所で精神科医療に長年携わった著者が、患者との交流を通してケアと生きることを考えた名著。あるとき、優れた詩人であった患者が倒れているところに出くわした著者は、彼が間の悪そうな表情をしているのを見て取り、失礼を詫びて立ち去る。治療よりも、みっともない姿をみられたくないという患者の尊厳をとっさに尊重した著者の振舞いに、究極のケアを見た気がした。(河村)

村上靖彦『摘便とお花見 看護の語りの現象学』
医学書院、2013年
医学的治療の担い手である医師と病や障害と生きる患者との〈あいだ〉に立つ存在として看護師を位置づけ、時間の経過や病状の変化のなかで、看護師がどのように患者に寄り添っているのかを、四人の看護師へのインタヴューとその分析によって鮮やかに描出する。「感情移入ではない」看護師の〈あいだ〉としての主体性の変容の構造的分析は、患者自身の主体性の変容を鏡のように映しだす。(木内)
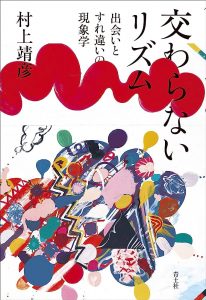
村上靖彦『交わらないリズム 出会いとすれ違いの現象学』
青土社、2021年
病気になると、私たちはある種のズレの感覚を体験する。村上はこの感覚を「ポリリズム」という観点から、現象学的な質的研究という手法を用いて明らかにしようとする。生理的なリズム、内的なリズム、社会的なリズム――私たちの体験には実に無数のリズムが介在し、それは知らぬ間に見事にチューニングされている。だが病気になるとこれらのリズムのズレが前景化する。村上は精神医学の理論的知見を様々な事例にフィードバックしながら、看護師の存在をこのズレを可視化しうる契機として分析して見せる。(木内)

川口有美子『逝かない身体 ALS的日常を生きる』
医学書院、2009年
ALSの母とすごした十二年の記録。しゃべることのできない母とのコミュニケーションは、汗の量や皮膚の状態といった生理的物理的な情報を介して行われる。「魂の器である身体を温室に見立てて、蘭の花を育てるように大事に守ればよい」と。ケアの大変さと面白さは、相手の体を通して、頭で理解していたことと全然違う出来事が起こり続けることだと思う。(伊藤)

市川沙央『ハンチバック』
文藝春秋、2023年
金原ひとみをして「読後しばらく生きた心地がしなかった」と言わしめた小説。著者は筋疾患先天性ミオパチーによる症候性側彎症の当事者で、人工呼吸器をつけ、電動車椅子で生活をしている。ケアは「沿うこと」などと言われるが、この小説には沿うことを決して許さない。安易な同調を跳ねつける、「無調」の音楽。(伊藤)

坂口恭平『自分の薬をつくる』
晶文社、2020年
躁鬱病の著者。「4時に起きて10枚原稿を書く」など毎日の日課を作ることが、彼にとっては調子を維持するための薬になっている。そもそも私たちはケアを医者や看護師といった専門家に任せすぎているのではないか?病気とともにうまく生きるような健康のあり方を、自分で定義することもできるのではないか?ワークショップ仕立てでケアを取り戻す方法を実感させてくれる本。(伊藤)

ジョアン・C・トロント『ケアするのは誰か? 新しい民主主義のかたちへ』
岡野八代訳、白澤社、2020年
英語の「care」は配慮する、関心を持つといった意味を持つ。したがってケアは福祉や医療に限定されるものではなく、世界を維持し人との関わり継続するためのあらゆる活動を含んでいる。それゆえケアはすべての人々が関わる問題であり、誰もがケア責任の配分に参加する権利を持つ。政治学者トロントはケアと民主主義が不可分の関係にあることを提示する。(河村)

伊藤亜紗他『「利他」とは何か』
集英社、2021年
「未来の人類研究センター」の初期の利他研究の成果ともいえる書籍。合理主義、贈与、物と命、責任と意志、小説の系譜と考察される対象はさまざまであるが、各論から引き出される見解は、利他の土台には偶然性があること、そして偶然性を可能にするには人間が「うつわ」となることである。(河村)
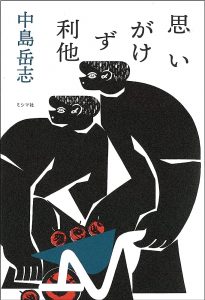
中島岳志『思いがけず利他』
ミシマ社、2021年
他人にとって良かれと思ってなされる利他行為は、ときに押し付けがましさや自己満足、あるいは無意識のうちの見返りの要求を伴っていたりする。著者は、ともすればすぐに「利己」へと転化する利他の「胡散臭さ」を睨みながら、落語、仏教思想、ヒンディー語、宇多田ヒカルの歌詞などに利他の扉を開くヒントを探る。行為者の意図を越えて受け取るときに起動するという偶然性は、センターが考える利他の基本的理念ともなっている。(河村)

伊藤亜紗、村瀬孝生『ぼけと利他』
ミシマ社、2022年
著者の一人である村瀬は「宅老所 よりあい」の代表であり、ぼけをもつお年寄りと日々関わっている。いわば何をし始めるかわからない「他者」と付き合うプロである。本書はそのような村瀬と「他者」の身体に関心を持つ伊藤が書簡を交わす。お年寄りとの想定外の出来事に対する二人の鋭く温かい考察は、ニーズに対応する従来のケアを超えた利他の可能性を開く。(河村)

ジョアン・ハリファックス『コンパッション 状況にのみこまれずに、本当に必要な変容を導く、「共にいる」力』
海野桂訳、英治出版、2020年
仏教者であり、かつ医療人類学者でもある著者。刑務所でのボランティアやネパールにおける移動診療など、現場でのケアの実践にもとづいて書かれた利他の本。利他に含まれる毒に対する警告が参考になる。魚を与えるのではなく魚の釣り方を教えるにはどうしたらよいか。2023年3月にリベラルアーツ研究教育院を退職した中野民夫先生推薦。(伊藤)

ティム・インゴルド『メイキング 人類学・考古学・芸術・建築』
金子遊他訳、左右社、2017年
設計図を描いてその通りに組み立てることは、優れたものづくりの方法なのだろうか?素材である枝の抵抗を感じながら籠を編み、時計職人は無数の部品をその都度調整しながら時計を完成させる。素材、作り手、環境の間のコレスポンダンスを重視するインゴルドのものづくり論は、ものと人間、自然と人間との間にも利他が働く可能性を開く。(河村)

ボリス・グロイス『流れの中で インターネット時代のアート』
河村彩訳、人文書院、2021年
美術作品は人間や普通の事物と同じく時間の経過によって滅びるが、美術館に収蔵されることで修復、保存、管理という「ケア」を受け、永遠の命が保障される。このような「ケア」に値するだけの美術作品の価値はどのようにして生まれるのか。グロイスのケア論がこれまでの芸術制度の考察の上に成立していることがよくわかる。(河村)

